長岡京市立図書館の棚から
長岡京図書館で借りた本から、これは!と思うものを選んで紹介しています。オーエン・コルファー『アルテミス・ファウル オパールの策略』

|
『アルテミス・ファウル オパールの策略』 オーエン・コルファー Eoin Colfer著 2005年 原題:Artemis Fowl (The Opal Deception) 翻訳:大久保寛 角川書店 〈長岡京市立図書館の成人図書の棚から〉 シリーズの4巻目まで読みました。傑作と思う。高尚な名作ではなく、お笑い・サスペンス・ハイペースなアクションなどの、まっとうな娯楽系の傑作です。テンションの高さ、密度の濃さが一貫していて、ヌケがない。 第6巻まで読み切ってしまいたいところですが、残念ながらこれ以降の邦訳がありません。日本で人気が出ないのはわかるような気がします。そのシニカルでビターなテイストが合わないんでしょう。日本で売れるには少々ユルくないと無理。あざとい「泣き」も入ったほうが一般受けする。そんなつまんない作り方に背を向けてしまうのがオーエン・コルファーのやり方なんでしょう。 内容については、第1巻紹介のときに少し書いたけど、補足が必要です。物語のメインは凶悪な悪党と戦う妖精警察偵察隊の活躍です。第1巻では偵察隊と天才少年泥棒のアルテミス・ファウルが対決しますが、以降は相手の能力を利用する形で手を結び、冷酷な巨悪に立ち向かうというストーリーになっていきます。 実質的な主人公はエルフのホリー・ショート警官ですが、彼女とアルテミス・ファウルがシリーズの中心となってストーリーを引っ張っていきます。二人をフォローする仲間たちがそれぞれに魅力的で、特に潜入プロの泥棒ドワーフ、マルチ・ディガムズが大好きです。臭くて汚くて貪欲で大食らいで、いちばんの趣味がひとの神経を苛立たせることという、ネガティヴだらけのやつなんですが。 このシリーズをなるべく多くの人に読んでほしい。面白さに目覚めてほしい。そして、第5巻以降の邦訳出版につながってほしいという願いを持っています。 既刊の残りを挙げておきます。 第2巻『アルテミス・ファウル 北極の事件簿』 第3巻『アルテミス・ファウル 永遠の暗号』 船越聡 2009.8.11 |
オーエン・コルファー『アルテミス・ファウル 妖精の身代金』

|
『アルテミス・ファウル 妖精の身代金』 オーエン・コルファー Eoin Colfer著 2001年 原題:Altemis Fowl 翻訳:大久保寛 角川書店 〈長岡京市立図書館の成人図書の棚から〉 非常に面白い。一冊にファンタジー・SF・アクション・サスペンス・コメディ・ヒューマン、てんこ盛りで面白い要素をすべてぶち込んでるから、面白いのが当り前。おまけに愛らしいヒロインのキャラにも引き込まれる。 個人的にはシニカルなテイスト部分がお気に入りです。甘ったるいのは大嫌い。ただちょっと、ひっかかる点がある。エンドのトリック部分が釈然としない。ここはネタバレ領域なのでほとんど書けません。トリックそのものも納得いかないし、明らかにおかしい部分がある。妖精は、次元の異なる世界に脱出していて手の届かないところにいる人間には魔法をかけられません。 アイルランドの妖精世界の住人たちとアルテミス・ファウルという泥棒一家との戦争がストーリーの中心ですが、かなり気になった点は、妖精世界が人間以上に高度なハイテク社会だという点です。この小説をユニークなものにしてるポイントなのですが、それってありうることなのかな。魔法というテクノロジーを手にしているのにハイテクまで手に入れようとするかな。魔法を使えない人間こそ、ハイテクを持つにふさわしいと言える。 それらの点を除けば文句なしに楽しめる物語です。徐々にテンションが上がって一気にラストまで直行。 オーエン・コルファーの著作はまだ2冊しか読んでないのです。もう1冊は『ウィッシュ・リスト 願い、かなえます』。ともにファンタジーです。登場するのはすべて欠陥人間か悪党。まともなキャラクターは登場しない。きれいごとやタテマエごとを言う輩もいない。非情に心地よい。 登場するキャラクターの中で。ホリー・ショートというエルフの女性警官が実質的に主人公です。あまり優秀ではない警官。12歳の子供(アルテミス・ファウル二世)に誘拐されてしまうという情けない警官。情けないながらもけなげに反攻を企てるのが愛らしい。彼女の魅力が作品の中で大きなウェイトを占めている。 後書きでは映画化が進行中とあるが、残念ながら完成作品はないし、今現在、制作の気配がまったくない。ファンタジー映画はすでに下火になってしまっている。映画観客はCG使いまくりのファンタジーに飽きてるので、作られる可能性はほとんどない。 船越聡 2009.6.12 |
ケイト・トンプソン『時間のない国で』上下巻
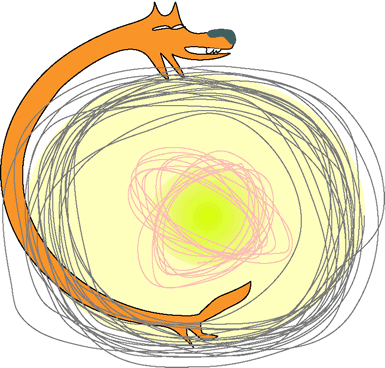
|
『時間のない国で』上下巻 ケイト・トンプソン Kate Thompson著 2005年 原題:The New Policeman 翻訳:渡辺庸子 東京創元社 〈長岡京市立図書館の成人図書の棚から〉 上下巻あるうちの上巻を読んでたとき、「こりゃ選択ミスだな」と思いました。しかしなんとなく引っかかる部分もあって、下巻も読んだのです。 何がだめだったのか。ファンタジーだけどリアリティが欠如している。リアリティのない、人間を描けてもいないファンタジーはただの絵空事にすぎない。好き勝手なことを書いてる文章を読んでも空しいだけです。 しかし下巻で展開に勢いが出た。サスペンスの要素があり、アイルランドの伝承や神話が節操のないほど大量に取り込まれる。シーンにちなんだ伝承曲や自作曲の楽譜を各章の末尾に入れる。なんでもありのてんこ盛りで、話は収拾するまもなく転がり続ける。面白くて一気読みでした。収拾がつくのかと心配になる展開ですが、最後には行方不明者が約一名出るほかは無事に収束してます。 アイルランドで時間の進み方が速くなり、時間が足りなくなっている。フィドラー(ヴァイオリニスト)の少年がティル・ナ・ノグ(極楽浄土みたいなところで時間の存在しない国)へ、失われた時間を取り戻しに行く。話ははるかに複雑だけど、紹介はこの程度にしとかないときりがない。 アイルランド特有の単語(ハーリングとかケイリーとか)が頻発してまごつくかもしれない。下巻のうしろにちゃんと用語解説集がついてるのです。わからなくても話がわからなくなるということはありませんけどね。 ケイト・トンプソンはチャリティオークションで自作の登場人物になる権利を出品していて、その人物が重要な役で登場します。上記の行方不明になってしまう人がそれなんです。金払って権利を得た人は怒らなかったんでしょうか。 アイルランド文化の入門書としてもころあいの本ではないかと思う。というか、アイルランド文化に少しは興味をもってほしい。アバウトでいいかげんで面白い世界ですよ。 船越聡 2009.5.4 |
草野たき『メジルシ』
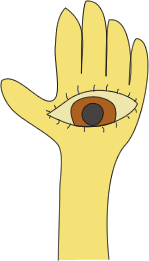
|
『メジルシ』 草野たき著 2008年 講談社 〈長岡京市立図書館の児童図書の棚から〉 面白い本を見つけ出すための確立された方法論を持ってないことに気づきました。図書館の棚から抜いてパラパラめくり、ちょっと読んで、「うん、これでいいんじゃない」と思ったら借りるだけ。直感のみに頼っている。だから疲れてるときは何もひっかかってこない。 草野たきの『メジルシ』にはピピッと反応しました。前回紹介文を書いたラウラ・ガジェゴ・ガルシアの『漂泊の王の伝説』と同じです。著者の名前すら知りません。でも絶対面白いと感じる何かがあるんです。それが何なのか。感じるプロセスを分解して体系立てたいと思うんですが、無理でしょうか。 『漂泊の王の伝説』がストーリー山盛りてんこ盛りなのと対照的に『メジルシ』はシンプルです。親子三人が離婚する前に北海道へ三泊四日の家族旅行をする。離婚を言い出したのは母(美樹)。父(健一)はまじめで気のいいサラリーマン。不倫などは考えられない善人です。 ストーリーが極限まで小さいかわりに、中三の娘(双葉)の心の変化をていねいに描き出す。双葉は父親を「健一くん」、母親を「美樹さん」と呼ぶ。本人に対してではなく、心の中で。あるいは心を許せる友人の前だけで。名前で呼ぶことで関係を客観視し、両親と一歩距離を置いている。意識しないままにやっていることなので、なぜ距離を置きたいのかなどということは当然考えていない。 呼び名ということでは、母親の美樹は実母を一貫して「あのひと」と呼び続けている。実母は少し前に亡くなっている。死んでも「あのひと」と呼び続ける。突き放したような冷たい言葉の響きから、生涯「あのひと」を許さないという強い気持ちが伺える。 家族の再生はないが、自身の問題に向き合い始め、個人を再生させるきっかけを示して終わる。双葉の中で「美樹さん」が「お母さん」に切り替わった。それぞれの勝手な物語世界から離れ、同じ現実世界の中で初めて対話したのではないだろうか。 たった四日間の時間経過の中、目立ったストーリーはなくても濃密なドラマがある。シビアで切れ味鋭い辛口なドラマ。自分の感性にぴたりとはまった小説だった。 船越聡 2009.4.21 |
ラウラ・ガジェゴ・ガルシア『漂泊の王の伝説』

|
『漂泊の王の伝説』 ラウラ・ガジェゴ・ガルシア Laura Gallego Garcia著 2002年 原題:La Leyenda del Rey Errante 翻訳:松下直弘 偕成社 〈長岡京市立図書館の児童図書の棚から〉 棚から手に取っただけで手応えが伝わる本。見たことも聞いたこともないタイトルと著者だったけど、迷わず借りました。 予想通り、傑作。児童書で300頁ほどですから、さほど長くありません。短いとさえ言える分量の中にめまぐるしく変転していく物語がぎっしり詰まっている。スピード感とドライブ感に酔わせられる。 著者はスペイン人ですが、7世紀ごろのアラビア半島を舞台にした冒険小説です。王子が一市民の詩作の才能をねたんだことから大きな過ちを犯してしまう。その悔悟とつぐないのための旅の物語です。例によって、ストーリーについてはここまでしか触れません。いくら書いても、読んでもらえなければ面白さがわからないのですから。 感覚が新しいと思ったら、ずいぶん若い人だ。そしてずいぶん多作だ。 作品リスト 翻訳されてるのはこれ一作きりらしい。デビュー作の『この世の終わり』はまだ邦訳がないのか。これ以上は読みたいと思っても現時点では読めないのが残念。 ただちょっと惜しいなと思うのが、エンドはきっちりきれいに丸く収まって大団円になることです。ストーリーが転げ回って破綻しまくったエンドでも、個人的にはよかった。さすがに商業出版ではそんな規格外れの冒険はできなかったんでしょうか。かなり前に紹介した荻原規子の『これは王国のかぎ』はそのノリで、めちゃくちゃ破綻している面白さがあった。『漂泊の王の伝説』はそれとちがってまじめな悔悟の物語ですからね。このエンドで(世間的には)よかったんでしょう。 ちなみに原題は邦題そのまんま。「放浪の王の伝説」です。 船越聡 2009.4.4 |
キャサリン・パターソン『聖なる夜に』

|
『聖なる夜に』 キャサリン・パターソン Katherine Paterson著 1995年 原題:A Midnight Clear 翻訳:ゆあさふみえ あすなろ書房 〈長岡京市立図書館の成人図書の棚から〉 八つの短編が収録されている短編集。それぞれ平凡な民のささやかな喜びが、クリスマスの季節をバックにして描かれている。傍目に見ればたいしたことでなくても、登場人物たちにとっては大事なひとときの体験なのです。 直前に読んだのがのカレン・キングズベリーの『赤い手袋の奇跡』シリーズ。ちょっと感動はしたんです。しかし三冊も読むと嘘くさい感動ドラマが甘すぎて、後味の悪さがまとわりついてきたのでした。奇跡の物語だといっても、あまりにもリアリティのないご都合主義の話を何作も作られては、いいかげん白けてくるのです。 キャサリン・パターソンのこの短編集は同じクリスマスの連作ではあっても、その対極にあるものです。現実感のある人物。それは彼女の長い人生経験から得られている、深い人間洞察のたまものです。 第三話「主のしもべ」に登場する女の子レイチェルはクリスマス劇でマリア役を熱望したのに、全配役の代役を命じられ、すっかりへこんでしまう。しかし当日に起こった思いがけないアクシデントによる大逆転劇は、奇跡などという甘いものではない。一瞬のチャンスを逃さなかった彼女の意志の強さによるものです。 やさしさと、軽やかなユーモアが全編を包み込み、気持ちのよい読後感を残す。そんな本でした。 船越聡 2009.3.23 |
ルーマ・ゴッデン『ラヴジョイの庭』
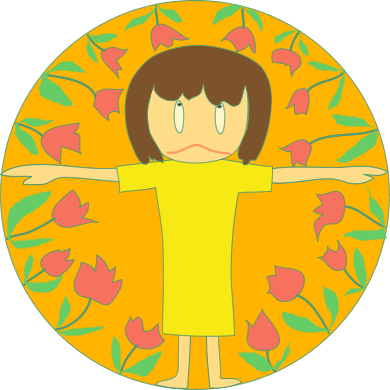
|
『ラヴジョイの庭』 ルーマ・ゴッデン Rumer Godden著 1956年 原題:An Episode of Sparrows 翻訳:茅野美ど里 偕成社 〈長岡京市立図書館の児童図書の棚から〉 読みやすい文章ではありませんでしたが、この一年に読んだものの中でベストでした。少なくない登場人物がすべて活き活きと活写され、ビターなストーリー展開はラストまで手綱をゆるめない。大満足で読了しました。 まず、読みづらい理由を挙げておきましょう。登場する人物名が多い。エピソードの中へひんぱんに過去あるいは未来の会話が挿入される。この点はそうとう面食らうと思います。福永武彦の『忘却の彼方に』は一人称と三人称が予告なしにころころ切り替わって戸惑ったが、これも読んでいてかなり混乱する。児童向けだが、児童に読めるのかと心配する。もう一つ、主人公のラヴジョイがなかなか登場しないこと。40頁読んでようやく現われる。現われるというより、暴力的に割り込んでくる。 ラヴジョイは事実上の孤児。11歳の女の子。彼女は人目につかない空き地を見つけ、ひそかに自分の庭園を造っていく。 訳者があとがきに書いてるが、これは熱情の物語です。自らの価値観を信じ、信念を曲げない。美に対するこだわりの強さは一人前のアーティスト並みだ。そのエネルギーに引きずられて手伝う羽目になる少年ギャングのリーダー。そのエネルギーに感応し、影響され、勇気を与えられる中年女性。読んでるこちらまで元気と勇気とやる気が出てくる。 何かを成し遂げた人間は、たとえそれが失敗に終わったとしても、当人が意識しないうちに自信となって積み上がっている。ラヴジョイは先々、とてつもない大きなことをしてくれるのではないか。そんな予感が濃厚な余韻として残る。 ルーマ・ゴッデン(ルーマー・ゴッデンと表記することもある)は他に『ディダコイ』と『人形の家』だけしかまだ読んでません。僕は世評の高い『人形の家』より『ディダコイ』のほうが好きです。『ディダコイ』もまた孤児の話なのですが、テイストはまるで違います。どちらも陰気な話ではないという点は同じですが。 英国にはすぐれた物語を綴る作家が大勢いる。特に女性のほうに多いと感じるのだけど、僕の感性がそちらに近いだけかもしれない。ゴッデンの小説は、図書館にあるもの、ひととおり全部読むことにしました。 船越聡 2008.11.25 |
岩瀬成子『そのぬくもりはきえない』
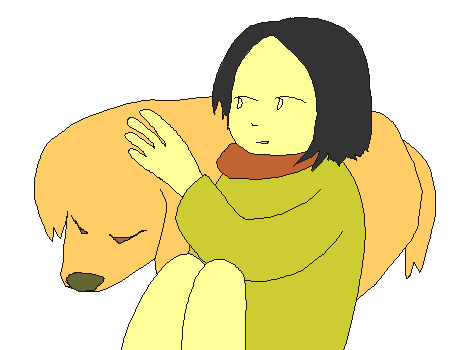
|
『そのぬくもりはきえない』 岩瀬成子(いわせ・じょうこ)著 2007年 偕成社 〈長岡京市立図書館の児童図書の棚から〉 タイトルと、考え深げに座っている女の子と大型犬の表紙絵(酒井駒子)に魅かれて借りました。岩瀬成子の名前は知ってましたが、読むのは初めてです。 読み始めて、何もかもが僕の好みに合っていると知りました。現実生活に根ざしたファンタジーで、特定の地点で時間のずれが生じている。時空のひずみは僕自身、好んで書いている。この本の中では空間のずれはないようだ。 主人公の羽村波は小学校4年生の女の子。時空のひずみをすり抜け、過去と現在を行き来する。大人なら常識観が壁になって事態を受け入れられないが、子供はやすやすと乗り越えてしまう。過去世界にいる同年配の男の子との出会いが物語の軸になっている。 僕はシビアでシャープでエッジの立っている文章が好きだ。ゆるゆるのぬるい甘い文章がだめ。きれいごとばかり並べてたり、ご都合主義的な展開が続いたり(フィリップ・プルマン、とか)、趣味的な領域で一人遊びしてたり(フランク・ライマン・ボーム、とか)、自己のイメージを表現する力が未熟であったり(上橋菜○子、とか)いうのは好きではない。岩瀬成子の文章は以上をすべてクリアしている。さりげなく読者のイマジネーションをかき立てている。 この話、現在の「男の子」との再開をエピローグとして書きたくなるものだけど、それをやらない。その潔さも好きだ。 岩瀬成子には他に何があるのかぜんぜん知らない。図書館にあるものを調べてみよう。 直前に読んだ石森史郎の『ゴンザ』(ポプラ社)も近年の作だけど、これも注目に値する物語なので、あわせてお薦めしたい。こちらはファンタジーではなく、歴史物です。 船越聡 2008.10.5 |
ウィリアム・メイン『闇の戦い』

|
『闇の戦い』 ウィリアム・メイン William Mayne著 1971年 原題:A Game of Dark 翻訳:神宮輝夫 岩波書店 〈長岡京市立図書館の児童図書の閉架から〉 ウィリアム・メインはまだ四つの小説しか読んでないのだが、どれもきわめて水準が高い。どれも、人物像がきわめて明瞭で、奥深く描かれている。安心して作品世界に身をゆだねることができるのだ。 『闇の戦い』は20年以上前に二度読んでいて、今回が三度目。ほかに読んでいる三つの小説(『夏至祭の女王』『地に消える少年鼓手』『山をこえて昔の国へ』)とちがって、そうとうに重苦しい。読みやすいとも言えない。 主人公の少年が現代と中世の二つの時空を行き来するのだが、前触れも入り口も何もなく、唐突に切り替わる。読みづらさの最大の要因はここにある。慣れてくれば、「ああ、このへんでトリップするな」と読めてくるのだけど。 少年は現代では重病で臥している父親の苦痛の声にさいなまれ、中世では村人たちを襲う強大な怪物(原作ではwormとのみ書かれる)を倒す戦いに参加させられる。どちらにしても逃げ場のほとんどない閉塞感がある。 英国文学を代表する小説の一つと言っても過言ではない作品だが、なにゆえ僕がこの重たい小説の魅力にとりつかれたのかが不思議だった。三度目にしてようやくそれがわかった。事情があって、年の離れた両親は息子に愛情をあまり示せていない(これを読むかぎりでは、まったく)。少年は本当の親子かどうかを疑い、両親に対して親愛の情を持てない。これは僕の両親との関係とそっくりだ。だから強く魅かれたのか。 この小説は過剰な説明をしない。怪物が何を象徴してるのかは読者の考えにゆだねられる。結末も潔いほどに少ない言葉で語られるので、うっかりすると事態を読み落としかける。簡潔であるがゆえに強い余韻を残す、すぐれた終わり方だと思う。 あんまり重たい小説はごめんだと言われる方は、先に挙げた『夏至祭の女王』『地に消える少年鼓手』『山をこえて昔の国へ』あたりをどうぞ。楽しめると思います。僕もこのあと、読めるかぎりメインの小説を読んでいきたいと思います。 船越聡 2008.7.22 |
ロバート・シェクリイ『無限がいっぱい』(短編集)
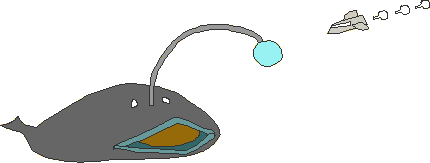
|
『無限がいっぱい』(短編集) ロバート・シェクリイ(ロバート・シェクリー)Robert Sheckley著 1960年 原題:Notions: Unlimited 早川書房 〈長岡京市立図書館の成人図書の棚から〉 異色作家短編集の9巻目。12の短編が収められています。 SF小説が無性に読みたくなって、見つけたのがこれでした。これは大当たりでした。荒唐無稽と奇想天外の極みです。シェクリイの小説は、この中の『ひる』The Leech 以外は読んだことないと思います。名前じたい、覚えがなかった。 かつてはハヤカワや創元文庫のSF小説をちょくちょく読んでいたものですが、SFのみの愛好者というわけではありませんでした。いつしか書店からSFが消えていくに従い、読まなくなってしまいました。今の若い人はSF小説の存在じたいを知らないのではないかと思うほど、消え去って久しい。 なぜ消えたのかを詮索する気はありません。とりたててこのジャンルにこだわる気はないんです。ノスタルジーとかいうこともなく、単にSF小説が読みたくなったのです。自由自在な発想とイメージに魅かれるのでしょうか。その発想の自由さ、ユニーク度において、『無限がいっぱい』は満足するに値するものでした。 いずれも平均して面白いが、『先住民問題』The Native Problem はとりわけ気に入っている。地球から遠く隔たった惑星に青年が一人で入植したあと、入植者グループを乗せた宇宙船がやって来るという話。青年は数か月で惑星に到着したけど、入植者グループが地球を飛び立ったのは百年も前で、技術レベルの違いから到着があとさき逆になってしまっている。青年が彼らを追い越して到着しているという話を信じず、彼をこの星の先住民だと誤解することから発生するトラブルを面白おかしく描いている。 12もある短編をそれぞれ紹介してると大変な分量になるし、その面白さを伝えられるという自信もない。とにかくこれは読んで楽しんでもらう以外ないと思う。 船越聡 2008.3.24 |
ローズマリー・サトクリフ『闇の女王にささげる歌』

|
『闇の女王にささげる歌』 ローズマリー・サトクリフ Rosemary Sutcliff著 1978年 原題:Song for a Dark Queen 評論社 〈長岡京市立図書館の成人図書の棚から〉 紀元1世紀、ブリテン島南部のケルト部族イケニの女王であるブーディカの伝記小説です。ブーディカは理不尽なローマ帝国の圧制に対し、敢然と叛旗をひるがえし、最終的には敗れて散った女性です。 著者のサトクリフはブリテン島で敗者の歴史を背負ったケルト人を主人公にした歴史小説を数多く書いています。中でも、アングロサクソンとの戦いを描いたローマン・ブリテン三部作『第九軍団のワシ』『銀の枝』『ともしびをかかげて』(すべて岩波書店)は、いずれも彼女の代表作に挙げられる。 この『闇の女王にささげる歌』は、その三部作より前の年代の、ローマ帝国による統治時代のもので、この時代をサトクリフが書いたのはこれが唯一ではないかと思います。 二千年もの昔の人々、生活を描きながら、同時代に立ち会っているかのような臨場感を伝える彼女の筆致は、これまでに読んだ諸作品と同じながら、見事だと思う。その時代の人々の喜び、悲しみ、怒りがリアルに伝わってくる。 歴史的に知られた叛乱を描いてるので、結末は知っている。知っているがゆえに悲壮感があふれる。多くの部族を糾合してローマの軍勢に当たっただけに、戦闘慣れしたローマ軍の策に乗らなければ勝利した可能性が高い。しかしそれでも、ローマ帝国がまだまだ強大だった時代なので、いずれは敗退しただろうなとは思います。 『闇の女王にささげる歌』はローマン・ブリテン三部作に劣らない名作と思います。ぜひケルトの女王に関心を持っていただき、一読していただければと思います。 ボアディケアというローマ帝国側の読みをすることもありますが、英国ではブーディカという読みが一般的なようです。英国人にはよく知られた英雄ながら、他の国ではほとんど知られていない。映画化やドラマなどは数あるものの、英国以外ではほとんど紹介されていないのです。映画は最近作られたものがありますが、これも日本で公開される見込みはほとんどない。 船越聡 2008.3.13 |
フィリップ・プルマン ライラの冒険シリーズ
『黄金の羅針盤』『神秘の短剣』『琥珀の望遠鏡』

|
ライラの冒険シリーズ 『黄金の羅針盤』『神秘の短剣』『琥珀の望遠鏡』 フィリップ・プルマン Philip Pullman著 1995年、1997年、2000年 原題:The Golden Compass、The Subtle Knife、The Amber Spyglass 翻訳:大久保寛 新潮社 〈長岡京市立図書館の成人図書の棚から〉 どっちかというと、児童図書の棚に入れるべきものでしょうけど、子供に独占させるのは惜しい。読んだのは単行本だったけど、文庫が出てるし、購入して児童図書のほうへも入れるべし。映画化もされている。たぶん子供たちのほうがずっと読みたがると思う。成人図書のほうではなぜかほとんど借り手がなく、悠々で借りられました。 ただこの作品、子供向けというには少々難しい部分があるかもしれません。神の存在という欺瞞、全否定、神そのものに対する謀反。そんなテーマは日本の子供たちには厳しいものがあります。が、そんなものは無視して、ただの冒険物語として読んでしまうでしょうね。ユニークな世界の中で激しく変転するストーリーを追っていくだけで楽しいのですから、小難しいことを考えないほうがいいのかもしれません。 単行本で1600頁というヴォリュームはすごい量ですが、わりあい短期間に読めました。著者が7年かけて書いたものを一か月ほどで読んでしまったのです。3冊はそれぞれ独立した本になってますが、実は上中下なのです。独立しておらず、一つだけ読んでも意味をなしません。一冊ごとにキリがついてません。 欠点をあげつらうのはどうかと思いますが、大人の目で見るとストーリー展開やキャラクターの肉付けなどで、そうとう不満が出てきます。登場人物(人間に限らない)が多すぎるせいなのでしょう。交通整理がうまくいっていません。キャラクター造型の弱さも、多すぎることからきていると思います。主人公が危機に陥ると、入れ替わり立ち替わり、グッドタイミングで味方が駆けつけてくれるという展開が何度もくり返されると、「ああ、またか」という気になってしまいます。 それでも、数多くの独創的なアイディアやキャラクターやイマジネーションが楽しく、一読をお薦めしたくなります。車輪族は『オズ』シリーズからのイタダキだし、パクリはありそうですけど。 船越聡 2008.1.12 |
ゲーテ『きつねのライネケ』

|
『きつねのライネケ』 ヨハン・ウォルフガング・フォン・ゲーテ Johann Wolfgang von Goethe著 1794年 原題:Reineke Fuchs 翻訳:上田真而子 岩波書店 岩波少年文庫 〈長岡京市立図書館の児童図書の棚から〉 図書館で手に取り、そのまま引き込まれて一気に読み切ってしまいました。痛快と言い切ると語弊がありますが、面白かった。 動物たちを登場人物にした寓話です。主人公のライネケは、『ライラの冒険』シリーズのコールター未亡人(映画ではニコール・キッドマンが演じる役)も真っ青になるほどの、狡猾で極悪非道なキツネです。口先三寸でどんな人をも言いくるめてしまう点でも、この二つのキャラはそっくり。 結末をばらしてはいけないでしょうか。だめでしょうね。知らないで読んだほうがいいに決まってます。しかしそれを避けてしまうと、ただ「読んでください」としか書くことがなくなってしまうのです。 この作品の持つシニカルな視点は好きです。子供たちに読んでほしい本です。数多く出回ってる児童文学のほとんどからは、現実世界は見えない。この本は寓話であり、ファンタジーの装いを借りて、鋭い風刺を投げかけている。 短い物語なので、とにかく一読をお薦めします。インパクトは強烈です。 船越聡 2008.1.8 |
北村薫『スキップ』『ターン』

|
『スキップ』『ターン』 北村薫著 1995年&1997年 新潮社 〈長岡京市立図書館の成人図書の棚から〉 北村薫の〈時と人〉の三部作の第一作と第二作。第三作はこれから読みますけど、ぼちぼち書きたくなりましたので、ここらで紹介させていただきます。 『ターン』は平山秀幸監督によって。2001年に映画化されています。映画館でそれを観てから、いつか読みたいと思っていました。すぐに読めなかったのは、いつも貸し出し中になってたからだったと思います。 第一作目の『スキップ』から読みました。17歳の女子高校生が25年スキップして、42歳の母親になってしまう話です。この小説はおそらくすでに数多くのメディアで取り上げられ、絶賛されていることでしょう。 普通の女の子がいきなり若い時期を取り上げられ、おばさんになってしまう。自分の失ったものに正面から向き合い、喪失感を克服するまでが感動的に描かれる。自分の青春の最後の花火をささやかに祝うシーンは、あまりにもせつなく悲しく、思わずそこでストップしてしまった。 『ターン』は映画で観ているので、大筋を知っていて読むのですから、少し勝手が違いました。映画は元のストーリーを基本的にはいじってなかった。エンディングの運びは小説のほうに軍配を上げたい。引き締まったエンドは深い余韻を残した。 版画家をめざす若い女性が事故に巻き込まれ、昏睡状態に陥る。事故の瞬間から彼女の精神は肉体と分裂し、その時点までの一日間を無限にくり返すループ世界に入り込んでしまう。その世界には元の世界にあるものがすべてあるのに、生き物の姿だけが消えている。動かないもののみの世界で彼女は途方に暮れてしまう。彼女は戻れるのか。どうしたら戻ることができるのだろうか。 二つの小説に共通して、主人公の女性を生き生きと描き出す筆力があるからこそ、感情移入ができるというものだ。『ターン』の森真希という主人公は版画をやっている。僕はメゾチントこそやらなかったが、銅版画を少しやったことがある。そういうところから入りやすいということもあったのだろう。 読み終わって、無性に映画を観直したくなった。感慨が深まる気がした。 第三作は図書館になかったので買いました。幸い、文庫で出てました。本屋の棚に三冊並んでいました。全部そろえたいという欲求もありましたけど、僕は極力モノを所有しないという方針なので、曲げるわけにはいきませんでした。 船越聡 2007.6.11 |