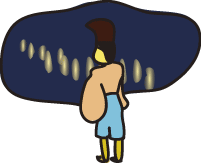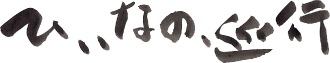 ひいなの巡行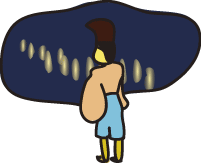
船越 聡
|
|
七つ年上の姉、由季の美貌を意識したのは、僕が12の時だった。 3月3日、雛祭りの夜、両親とほかのきょうだいたちはみな芝居見物に出かけていて、家の中は由季姉さんと二人だけだった。 僕は歯痛がひどくて部屋で寝ていた。のどが渇いて、白湯でも飲もうかと思って階下におりたら、居間からラヴェルのボレロが聞こえてきた。当時、ボレロの曲名は知らなかった。聞き覚えある、ぐらいの曲だった。 ぬるい湯を注いだコップを持ったまま、居間をのぞいた。居間には先週から、古めかしいが立派な七段飾りの雛壇が据えられている。雛壇の前で、由季姉さんが身をくねらせて踊っていた。 音楽はゆるやかにクレシェンドし、クライマックスが近づくにつれ、姉は一枚ずつ衣類をとった。下着だけになり、曲が終わってもなお、姉は踊りつづけた。姉の顔も体つきも肌も美しいと思った。 あとになって思い返せば、いくら踊りに夢中になってたとはいえ、僕が近くに立っていたことは気づいていたはず。姉はまったく頓着していなかった。 その時僕は、ただひたすら姉の肢体に見とれていて、歯の痛みも忘れた。僕は姉の魅力のとりこになってしまっていた。 その6年後、姉は婚約した。相手はビスマスとかクリソベリルとかの鉱物を取り扱っている若い実業家で、三十代はじめにして業績を軌道に乗せた起業家だった。 僕は気にくわなかった。姉を取られた無念さもあったが、ビジネス社会を生き抜いてきている、羽振りがよさそうで口先なめらかな商売人が姉にふさわしいと思えなかった。 姉は彼をどう見ていたのだろう。豊かそうに見える見かけだけでなびくタイプとは思えなかった。彼女の言動の裏側にはたいてい、隠れた理由がある。姉の心中は常にブラックボックスだった。 幼い時、姉に連れられてどこか遠くへ行った記憶がある。電車を乗り継ぎ、さらに歩いて、町中から寂しい田舎道。果ての見えない長い道を、二人きりでえんえんと歩いた。 僕は怖くなってきてうずくまった。姉は僕を叱りつけ、ついてくるようにと言った。 「わたしがついてるから大丈夫、怖くないのっ。どこまでも、どこまでも行くのよ、わたしといっしょに」 あの時の姉の言葉ははっきり憶えている。不思議なことに、あのあとどこまで行ったのか、どうなったのかは何も憶えていない。あの時以来、姉には「従わなければならない」という、呪縛のようなものが僕の中に根づいてしまった。 姉の結婚式は雛祭りの明くる日ということになった。毎年執り行っている雛祭りをすませてからにしたいという、姉の要望を容れた。 倉に豪勢な雛人形セットがある。素人目にはただの古ぼけた人形セットにしか見えないが、曾祖父の代に、魚津からの嫁入り道具のひとつとして新調されたものだ。 金屏風の前に有職雛、雛道具は昼顔の彩色絵の飯櫃、漆塗の違い棚、提子(ひさげ)、行器(ほかい)、駕籠(かご)、つづら、貝桶等々、ありとあらゆるものが揃っており、七段飾りの高さは人の背丈ほどになる。これだけ贅沢なものをしつらえるには、たいそう金がかかったろうと思う。当時の親の見栄以外のなにものでもない。 子供のころ、勝手に人形を並べて遊んでいて、父から大目玉をくらったことがある。こういうものは、気安くいじると祟るぞと言われた。 「どんな災厄をひっかぶってるかわからんのだから、大人でも取り扱いには神経を使っておる。なにも知らん子供は絶対に手を触れちゃいかん」 ああ言ってはいるが実は、高価なものを壊されちゃ困るもんだから、方便で言ってるんだと、子供心にもおぼろげながらに思っていた。 わが家は材木を商う問屋として、かつては羽振りがよかったそうだ。僕が物心ついたころは、すでに商売が傾いていた。 母は4人前に亡くなった。父は顔が丸っこくて温厚に見えるが、その実、意固地な性格だ。母がいたときは丸く収まっていたが、いなくなってからは、もともとあった心の中のトゲが表にあらわれるようになった。二人いる兄のうち、長兄は父と衝突して出ていった。 雛の祭りは、いつもの年は、最近の倣いで略式ですましてたのだが、この年ばかりは姉の婚約者も招き、本式の作法で宴席を持った。 栗赤飯に塩焼きの鱒、しじみの赤味噌汁、紅白のかまぼこ、茶わん蒸し、うどやわけぎのぬた、白酒に蒸し菓子。彩り鮮やかに盛り飾られた箱膳を前に、姉は満足げだ。この日は自分が主役と疑っていない様子だ。 上機嫌でみんなとお喋りしつつ、そのくせ誰をも眼中に入れていないように、僕には見えた。姉は得意げであり、上から目線で女王気取りだった。僕は不快さをこらえきれなくなった。来週提出予定のリポート用資料に目を通したいと、口実を言って自室にひきあげた。 大学へ進学するのを期に、家から出ることを決めた。親の反対を退け、遠くの大学の入試一本に絞り、合格した。 僕が荷造りに余念のなかったさ中に、姉の夫の会社から家へ、取り乱した声で電話がかかった。 姉の夫が死んだという突然のニュースに、家の中は騒然とした空気につつまれた。上半身血まみれで自室に倒れてたという。 「由季を出してください。由季はどうしてるのです!」と、父は受話器に向かって怒鳴った。 いくら捜索しても姉の姿はどこにも見いだせなかったそうだ。誘拐されでもしたか、あるいはもしや、みずから姿を隠したのか。何日たっても杳として行方が知れなかった。 「神隠しにでもあったのか」と誰かが言ったが、忽然と消えてしまった。 姉の夫を刺したナイフは邸内からすぐ見つかったが、外部から出入りしたものの形跡がまったくなく、殺害の嫌疑は姉に向けられた。しかし手がかりがなく、捜査は暗礁に乗り上げた。 1年後、事件の衝撃が薄らいで、大学生活を楽しんでいたころ、通例の雛の祭りを執り行いたいという、父親からの電話を受けた。明るい光のあふれる場から、暗い陰のさす実家に戻るのが億劫な気分だったが、いちじ帰郷することにした。 現われない姉を案じての祭りと承知していたのだが、やはり、いつになく寂しい雰囲気の宴だった。 「やはり、嫁入り道具として雛を持たせてやるべきだったな」父は雛壇を凝視して言った。 雛が災厄をすくい取るというのは本当なんだろうか。それが事実なら、家が左前になることもないだろうと、思い直した。雛の祭りをしたからといって、今まで特にいいこともなかった。 その夜、みなが寝静まったあとも、いろいろ考えごとが頭の中をめぐり、寝つけなかった。 それまで意識したことはなかったが、自分にとって家の存在が切実なものではなかったことに気づいた。頼りになる次兄が家にいる。家族の中においてさえも、僕という存在はそれほど意味を持つものではない。寂しさもあったが、反面、家から自由になれるという安堵の気持ちもあった。 思いが定まりかけ、しばらくうとうととした。小さな音で音楽が聞こえる。ボレロだとわかった。夢ではなく、現実に鳴っているのだと気づき、目が覚めた。 音を忍ばせて階下へおりた。居間は宴席のあとがきれいに片づけてあり、がらんとしていた。 暗い部屋の中、雛壇の前に、裾、袴の長い衣装を着た女がこちら向きに立っていた。女は僕に気づき、にこっと笑った。濃い化粧に彩られた女の顔は由季姉さんだった。 「姉さん、どうしたの、いったい。今までどこにいた。どうしてたんだよ」 姉はほほえむだけで答えず、部屋を横切って僕に近づいた。 その時、姉の背後の雛壇がからっぽであることに気がついた。人形も、雛道具も、何もかも消えて、段だけが残されていた。姉は、すうっと僕の前を通りすぎ、半ば開いた硝子戸から庭へおり、ひたひた歩いて出てゆこうとする。 「姉さん」 僕はあとを追った。 闇に白く浮かび上がる足袋が、ひたひたとひそかな音たてて、滑るように速く動いていく。 「はやくいらっしゃいな」 姉は、ちらとふりむき、艶やかな笑みを見せた。 僕は走って、姉に追いついた。 「どこへ行くの」 姉は、あごをしゃくって前方を指し示した。 おもての道は、いつになく街灯の明かりがなく、闇が深い。 すうっと延びる道の先に、一団となって進む行列がほのかに見えた。 「いらっしゃい。わたしがついてるから大丈夫。どこまでもわたしといっしょに来るのよ」 「怖いよ、なんだか。わけわかんないじゃないか」 大仰にあきれた表情で、姉は僕の顔を凝視した。 「お前は何もわかっちゃいないんだね。こんなつまんない人間界にいたってしようがないでしょう。何が楽しくってこんなとこに未練残してんだい」 と言い、姉はぐいっと僕の腕をとってひっぱった。 僕は畏れでふるえた。足がもつれ、ころびそうになりながらも、姉について小走りで前の行列を追った。 等身大の大きさの雛人形たちが、唄を歌い、舞い、管弦を鳴らして練り歩いていた。 わけもわからず涙が出てきた。 「めそめそするんじゃないよ!」姉は叱咤した。 「姉さん」 僕は訴えかけるように姉に言った。 「本当に姉さんがやったの。義兄さんを殺したってこと。ちがうよね」 「当たり前じゃないの。わたしが人殺しするわけないでしょ。あれは自分で勝手に死んだのよ」 姉は眉を吊り上げ、僕を軽蔑するように見た。 「事業がうまくいかなくなったから、ノイローゼになって自分を刺したのよ。口先ばっかりで弱い男。自殺したと思われるのがいやで、刃物を隠すようにとまで、わたしに指示したのよ。ナイフは適当なところに放り投げて、出て行ったのよ。あれ以上あそこにいたって、面白いこと何もありゃしないんだから」 姉は、しれっとした口調で言ってのける。 僕は前をゆく列を見た。みな、とても陽気で華やいでいる。 「それで、これからどこへ行くの?」 「この世の中は人間界ばかりじゃないんだよ。天上界もあれば地獄もある。餓鬼道や畜生道だって、ここより面白いものが見られそうよ」 僕が言う言葉も見つけられずにいると、姉さんはあきれかえった顔をした。 「お前は本当に何もわかっちゃいないんだね。わたしは人間じゃないのよ。官女のひとりが人間界に仮居しているにすぎないのよ。人間たちがほざいているように、わたしたちは人間界の災厄の形代(かたしろ)をひきうけているわけじゃないの。わたしたちはただ、人間たちの災厄を面白おかしく眺めているだけなのよ」 僕は、少しずつ過去のこと、いや、生まれる前のことを思い出し始めた。 「わかってきたのね。さあ、右近の君よ、列にお並びなさい」 僕は、どん、と姉に押された。いつのまにか、裃をつけている僕は、行列に加わった。 娘の貌(かお)ぞよき あな美しやな あれを三車の四車の愛行輦(あいぎょうぐるま)に打ち乗せて 受領(ずりょう)の北の方と 言わせばやぁ 耳になじみ、思い出す唄。 僕の心はしだいに弾み、声を出して、いっしょに歌った。 〈了〉 2017.12.24 |